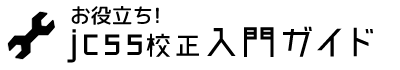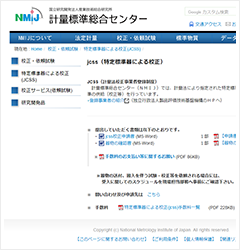お役立ち!jcss校正入門ガイド

より正確な校正結果のために
 計測器が正しい数値を占めているかどうかを保証するために、基準器による校正が必要です。そして校正を行う際、外部機関への依頼も選択肢の一つとなります。その際、その事業者がどういった認定状況で校正を行っているか、きちんと確認してから依頼を行った方が良いでしょう。
計測器が正しい数値を占めているかどうかを保証するために、基準器による校正が必要です。そして校正を行う際、外部機関への依頼も選択肢の一つとなります。その際、その事業者がどういった認定状況で校正を行っているか、きちんと確認してから依頼を行った方が良いでしょう。
従来の校正作業は、厳密な資格等がなく、発注者と受注者の信頼関係によって成り立っている面もありました。こうした信頼関係とは異なり、第三者機関(NITE認定センター)がその校正能力を認めているかどうかで、信頼性もまた異なってくるでしょう。
認定事業者は多数ありますが、どの事業者が適切か、判断するのは難しいことです。そこで当比較サイトでは、各メーカーのjcss校正能力を比較できるよう、情報を取りまとめました。より適切な選択ができるよう、あなたの手助けを行います。
JEMIC
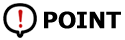
- JCSSの規格を満たした測定器の校正を行っています
- ISOなどの国際規格に準拠した校正を行っています
- どのメーカーの測定器でも校正が可能です
JEMICはjcss校正の認可を得ている事業所のひとつです。様々な測定器などの校正を特定二次標準器や常用参照標準器を使って行ってくれます。国際規格であるISOやFSSCに準拠した対応もきちんととることがJEMICは可能です。
測定器などを運用している会社などはISOなどの規格上、年に一度の校正を実施しなければなりません。校正を実施したという証明書は外部監査などによって必要となります。これらの国際規格に準じた証明書をJEMICではもちろん発行することが可能です。
JEMICでは様々な測定器の校正を実施可能です。メーカーを問わず製造年代を問わずどんな測定器の校正も可能です。校正に掛かる費用等の詳細はJEMICのホームページから確認が可能です。
JEMIMA
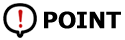
- 会員企業への競争力強化サポート
- 会員企業が新しいビジネスを実現するための支援
- プレゼンス向上を図るために行われる事業
産業のマザーツールの1つである電気計測器を提供する企業の集まりとしてJEMIMA(一般社団法人 日本電気計測器工業会)があります。様々な産業で使用される計測器には性能に関して整合性が求められ、ここではJISS(トレーサビリティの確保)が重要な位置付けとなります。JEMIMAでは機器の校正能力を国に代わって審査をする認定センターとして登録されており、現在、正会員・賛助会員含め28社がJCSS登録事業者になっています。JEMIMAではjcss校正のサービスを中心とした3つの事業が行われています。それぞれの事業がJEMIMAの強みであり、まず、グローバルな競争力強化のための会員企業サポートがあります。ここでは国内外規制動向調査事業や国際標準化推進事業、統計事業が設けられ、例えば、会員が海外事業展開に向けた支援を受けることもできます。因みに2017年時点では87社の正会員他、31社と10団体の賛助会員を有しています。
JEMIMAは新しいビジネスに対しての支援を行っています。会員企業が関心を持つ技術開発テーマなど、新しいビジネスを実現するための事業も手掛けており、学会や研究機関また官公庁との意見交換の場を提供するなど、会員は共同開発を行う際の支援を受けることができます。
事業には、JEMIMAのプレゼンス向上を図る内容があります。主な事業には広報・展示会・セミナー開催があり、会員は各事業に参加することで業績向上につなげることができるようになります。例えば展示会事業では、2017年に「計測展2017 TOKYO」が東京ビッグサイトで開催されています。セミナーも定期的に開催されており、特徴としてニーズに合わせたものや公的資格取得を目指すものなど、企業にとって有益な内容が数多くあります。
NITE
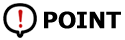
- 公的認定機関として、国際規格に基づいて認定してもらえる
- 最新の科学技術で対応してもらえる
- 安心した事業活動を続けることができる
NITEでは、様々な事業を行っていますが、jcss校正サービスも提供しています。この機構に依頼することで様々なメリットがあります。まず、公的認定機関ですので、国際規格に基づいて認定をしてもらうことができます。
この機構では、最新の科学技術をすぐに導入するようにしており、常に技術力の向上を行っています。そのため、常に世の中から遅れを取ることなく対応していますし、良い技術で良い校正を行ってもらうことができます。
しっかりとした校正をしてもらうことで、安心した事業活動を行うことができます。機構として、広い視野と高い適応能力を持ち、高い技術力で対応してもらうことができますので、安心して依頼できます。
HIOKI
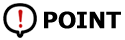
- 専門技術者が実施するので安心感がある
- 校正や調整・修理まで一括依頼が可能
- 必要に応じた校正・調整が選択できる
HIOKIは国際MRAに対応するJCSS認定事業者です。校正事業者の技術能力やトレーサビリティが確保された証明書を発行でき、知識や経験を豊富に持つ自社製品の校正専門技術者がjcss校正を実施するので安心して利用できます。
調整前の校正結果が規格内の場合でも再度校正する調整付校正(調整後確度保証付)や、故障診断後に修理や調整・校正をするなどが一度の依頼で対応が可能な会社です。販売店や直営サイト「修理・校正Direct」で見積もりを受け付けています。
調整後確度保証付の調整付校正や値付けのみ実施の校正、修理も可能ですが、校正ポイント・調整・一般校正などの実施は必要に応じて指定することができます。問い合わせは平日午前9時から12時、13時~17時に受け付けています。
小野測器
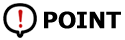
- 信頼性と安定性で測定された値を確実な値にする
- JCSS認定された民間第1号の公的機関
- 国際MRAに対応しているjcss校正
計測器で測定された値の精度を確実な値にするために校正をしますが、信頼性と安定性を高めるためには厚生された計測器を使います。小野測器では長年の経験とノウハウで信頼性の高さと高度な校正サービスが行われています。
音響・超音波のJCSS認定事業者として民間では第1号となった小野測器はFFTアナライザのjcss校正は国内初のサービスです。JCSSから公的に認められた公的機関で、(株)小野測器宇都宮テクニカル&プロダクトセンターで校正は実施しています。
国際MRAに対応しているjcss校正を行っています。校正結果はILAやAPLAC加盟国でも有効ですし、校正結果は一回OKがもらえれば、どの国でも受け入れられて再承認の必要もありません。校正範囲は小野測器のホームページにあるファイルで確認をすることができます。
NMIJ
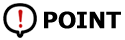
- 計量に関することが分かりやすく書かれているサイト
- 校正、依頼試験の情報が常に更新されるサイト
- 研究開発品の情報が値段まで記載されている
計量、jcss校正は、職種・業種を問わず多くのビジネスで利用される技術です。特に日本は製造業で栄えた国で、今後も日本経済との関わりが深く、就労される方の多くのかたにかかわりのある分野と言えるでしょう。その情報が掲載されているサイトが、NMIJ、計量標準センターのサイトになります。
計量やその対応製品に関心のあるかた、これからスキルを身につけて仕事に生かしていこうとお考えのかたはまずはこの計量標準センターの公式サイトをご閲覧ください。対象製品の情報も常に更新されていますので、今の最新技術、製品のことをすぐに確認することができるでしょう。
計量標準センターの中にはいくつかの部門があります。研究戦略部や工学計測標準研究部門など、技術開発や推進に関する部門があります。日本の工学技術はこちらのような研究機関によって高められているということです。
jcss校正を定期的に実施するなら
jcss校正を定期的に実施するなら、まずは校正周期を把握しておきましょう。原則として計測器の校正周期や校正の頻度をjcssでは規定していませんので、計測器を使用する事業者や個人のタイミングで行えます。安全性を重視するのなら、製品評価を参考にできます。jcss校正を依頼する事業者にとって、コストの負担はかかりますが、作業員の安全性を高めるうえでは効果的です。新しく作業員を募集する場合や、現場の士気を奮わせる意味での効果も期待できます。jcss校正を定期的な周期で実施すると、作業員も危機管理意識が高める可能性がでてきます。ちょっとした不注意が感電事故を引き起こす場合があるように、定期的な校正を実施して作業員が安全性を意識するように現場を調整できます。予算によって、隔年などでも実施できます。
電気系統の作業で、絶縁仕様の防具や保護服は、作業現場で一定の負荷にさらされます。目に見える傷がついていなくても、摩擦による軽度な摩耗が発生しますので、長年に渡れば保護効果が薄れるのが自然です。自然に経年劣化するものの、意識を高めてjcss校正を実施すると、経年劣化を抑制できる場合もあります。どのような状況下で摩耗しやすかったのかを検証できれば、作業環境を見直す機会にできるからです。校正の頻度を考えるときに、どうしてもマイナス面でとらえがちかもしれませんが、作業環境の見直しも含めた効率化と危機管理意識の高揚はプラスに作用します。経年劣化を指摘されたからといっても、すぐに全面的に計測器を新規交換しなければならないとは限りません。プラス思考で注意喚起としてとらえるのも、jcss校正の役立て方の一つです。
作業員にとっては、詳細が不明な状態で現場で作業することになりかねませんから、正式なjcss校正の証明書の存在は心強いです。新入社員はjcssの存在や認証を知らない場合もありますので、現場での教育の一環としても役立てられます。なぜjcssなのかを説明するときに、品質マネジメントシステムなのだと指摘すれば共通認識を形成しやすくなります。計測器と校正項目によっては校正証明書が発行されない場合もありますので、認証の他に校正ラベルの存在も情報として共有しておくと便利です。校正ラベルは幅広い用途で発行されています。jcss校正を実施する事業者も、NITE認定センターによって第三者の立場で審査されています。認定されているからこそ、校正結果が信頼されるシステムと言えます。jcss校正の証明書が、校正の結果を信頼できるものにしています。